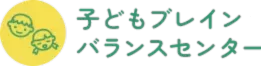【ゲーム脳とは?】子どもの脳の状態や成長に与える影響などについてプロが徹底解説!
「子どものゲーム脳が心配」
「ゲームばかりやっている子どもへの対処法や適切な対応が分からない」
スマホゲームやテレビゲームなど、幅広いジャンルのゲームが溢れている現代において、子どものゲーム脳は様々な視点から問題視されています。
とは言え、いくら「ゲームをやめなさい」と伝えても、思うように子どもが言うことを聞いてくれない、口論になってしまう、といった悩みを抱えている方も多いでしょう。
そこで今回は、子どものゲーム脳に焦点を当てて、ゲーム脳が問題視されている原因やゲーム脳が子どもの脳に与える影響、子どものゲーム脳を防ぐ方法などについてご紹介します。
また、ゲームが脳に与える影響などについては「ゲームは子どもの脳の発達に悪いの?良いの?どうしたら良いの?」でもご紹介しているので、気になる方はぜひこちらもご覧ください!
ゲーム脳とは
まずはじめに、ゲーム脳についてご紹介します。
ゲーム脳とは、スマホゲームやテレビゲームなどの影響によって、脳の発達が偏り、前頭部分の活動が低下した状態を指します。
ゲーム脳という言葉は、科学的には証明されていない非公式な言葉ではあるものの、ゲームを長時間プレイし続けることが子どもの脳の発達や健康などの面から良くないという側面から、幅広く世の中に浸透した言葉です。
とは言え、ゲームをプレイすること自体が悪いという訳ではなく、ゲームの種類や考え方によっては子どもの脳にプラスに働く場合もあります。
そのため、自制や自己管理が難しい子どもの保護者は、ゲームが子どもの脳や生活面に与える影響を正しく理解し、しっかりと教育に反映させることが重要なのです。
ゲーム脳はなぜ問題視されている?
次に、ゲーム脳(あるいは 子どもがゲームに集中してしまう状態)が問題視されている理由についてご紹介します。
一般的には、子どもがゲームに多くの時間を費やしてしまうことで学業が疎かになってしまったり、視力が急激に悪化してしまう可能性がある、などが ゲーム脳の大きな問題点として認識されています。
しかし、子どもがゲームに依存してしまうリスクは他にもあります。
例えば、ゲームの世界観と現実の区別が難しくなり、暴行や犯罪などの事件を起こしてしまうこと、さらにはそれに伴う生活習慣の乱れや運動不足、人とのコミュニケーション機会の減少などが挙げられます。
これらの問題は、実際に触れるゲームの種類によっても大きく異なる部分ですが、実際にゲームを通じて子どもの生活環境や考え方にマイナスの影響が及んでいる事例は多くあります。
これらの問題を解決するためには、子どもがゲームに依存する状態を避けるだけでなく、保護者や身の回りの大人がゲームに関する正しい考え方や関わり方を子どもに伝えることも重要です。
ゲーム脳が子どもの脳に与える影響
本項目では、ゲーム脳が子どもの脳に与える影響についてご紹介します。
前述したように、ゲーム脳とは、スマホゲームやテレビゲームなどの影響によって、脳の発達が偏り、前頭部分の活動が低下した状態を指す言葉であり、少なからず脳の発達に影響があることが知られています。
これは、ゲームをプレイすることで刺激される脳内の部位に偏りがあるために、前頭葉と呼ばれる部分の発達が周りと比較して遅れてしまい、結果として感情のコントロールや判断力、創造性などが損なわれてしまうことが原因です。
それに加え、就寝前にゲームをプレイすることで脳が活性化(興奮)してしまい、睡眠の質が下がってしまうことや、脳の休息や記憶の定着に影響があることも問題視されています。
また、ゲームによって繰り返し刺激される報酬体験は、日常生活における達成感や満足感を感じにくくさせる可能性もあるため、気付かぬうちに普段の生活自体にもマイナスな影響が出てしまうのです。
子どもの脳と発達の仕組み
ここでは、子どもの脳と発達の仕組みについて簡潔にご紹介します。
脳の成長は、人生における数多くの要素が複雑に絡み合うことで複雑に刺激され、特に幼少期の段階で急速に発達します。
食事や睡眠、日常で触れる新しい体験など、脳の発達に欠かせないものは多くあります。
そんな脳の発達に欠かせない各要素をバランス良く取り入れること同様に、脳への刺激においても、バランスを意識しなければなりません。
ご存知の通り、脳は様々な部位に分かれており、右脳や左脳、前頭葉、側頭葉、後頭葉など、部位によって働きや役割が異なります。
各部位が それぞれ異なる働きや役割を持っていながらも、互いが密接に関係して補い合っているからこそ、私たちは正常に意識を保ち、物事を正しく認識することができるのです。
しかし、ゲームをはじめ、脳への部分的な刺激が強いものに依存してしまうと、脳のバランスの取れた発達が損なわれてしまい、感情面や精神面、はたまた物事の考え方などに影響が及んでしまうのです。
そのため、あらゆる物事において依存や時間の割きすぎには注意する必要があり、特に成長期における子どもの生活習慣は、大人よりも慎重に考えなければなりません。
子どものゲーム脳を防ぐ方法
本項目では、子どものゲーム脳を防ぐ方法について、以下の4つをご紹介します。
- ゲームの時間を管理する
- ゲーム以外に好きなことを見つけさせる
- ルールを決める
- ゲーム脳によるリスクをしっかりと伝える
① ゲームの時間を管理する
子どものゲーム脳を防ぐ方法の1つ目は「ゲームの時間を管理すること」です。
多くの保護者の方が実践しているとは思いますが、子どもがゲームに費やす時間を管理するというのは、やはり重要な対策と言えます。
具体的な時間を定め、平日であれば〇〇時間、休日の場合は〇〇時間といった具合で、正確に時間を管理します。
しかし、急に時間による制限を設けたり、子どもの欲を無闇に制限してしまうと、子どもにとっても納得がいきません。
そのような場合は、子どもとコミュニケーションを取りながら、徐々に適切な時間を設定していくことが重要です。
また、子どもの手本として、テレビを見る時間やスマホを触る時間などを保護者自身が管理することも効果的です。
② ゲーム以外に好きなことを見つけさせる
2つ目は「ゲーム以外に好きなことを見つけさせること」です。
子どもがゲームに依存してしまう理由はいくつかありますが、やはり「ゲームが面白いから」というのが本人にとって大きな理由です。
つまり、ゲームよりも面白いことや熱中できるものがあれば、自然とゲームに費やされる時間は減っていきます。
子どもにとって面白いと感じるものや熱中できることは様々ですが、その「何か」を見つけてあげることで、ゲームへの依存を防ぐことができるでしょう。
③ ルールを決める
3つ目は「ルールを決めること」です。
時間の管理と重複する内容ではありますが、ゲームをプレイすること自体にルールを課すこともポイントです。
ルールの決め方は家庭によってオススメの方法が異なりますが、「宿題を終えてから」や「食事の後30分はゲームをしない」、「就寝1時間前には終える」といった具体的なルールは、子どもも納得しやすく、ルールとして課しやすいでしょう。
また、ルールを破った場合のペナルティなどについても事前に決めておくことができれば、より忠実にルールを守らせることができるでしょう。
④ ゲーム脳によるリスクをしっかりと伝える
4つ目は「ゲーム脳によるリスクをしっかりと伝えること」です。
ゲームの時間を管理したりルールを課すことは簡単ですが、重要なのは子どもがそれ自体に納得することです。
ゲームを制限する具体的な理由が理解できなければ、子どもは単に意味もなくゲームを制限されていると感じてしまいます。
子どものゲームの時間やルールを管理するためには、脳への悪影響があることや、ゲーム依存による恐ろしいリスクがあることをしっかりと伝えることが重要です。
ゲーム脳 / ゲーム依存症によるリスク
次に、ゲーム脳 / ゲーム依存症によるリスクについて、以下の5つをご紹介します。
- 前頭前野の発達に支障が出る
- 思考能力や集中力が低下する
- 勉強や他のことに割く時間が減る
- 協調性や社会性に影響する
- 現実との区別がつかなくなる
① 前頭前野の発達に支障が出る
ゲーム脳 / ゲーム依存症によるリスクの1つ目は「前頭前野の発達に支障が出ること」です。
前述したように、ゲームをプレイすることによる脳への刺激には偏りがあります。
特に、現代のゲームの中には視覚的にも強い刺激を伴うものや即時的な報酬系への刺激が極端に強いものも多くあります。
そのような刺激を脳に与えすぎてしまうと、前頭前野の発達が阻害される可能性があり、結果として 感情のコントロールが難しくなったり、計画的な思考や行動が取りにくくなったりすることがあります。
② 思考能力や集中力が低下する
2つ目は「思考能力や集中力が低下すること」です。
世の中のゲームの中には、瞬間的な判断や反応を繰り返すものも多く、じっくりと考えたり、長時間集中したりする能力を低下させる可能性があります。
特に、アクションゲームなどの刺激の強いコンテンツに長時間触れ続けてしまうことで、通常の学習や読書などで必要とされる持続的な注意力が失われるリスクがあります。
また、ゲームによってすぐに報酬や成果に辿り着くことに慣れすぎてしまうと、日常生活においてすぐに結果が出ないような物事や作業に対して憤りを感じてしまうようになってしまうこともあります。
③ 勉強や他のことに割く時間が減る
3つ目は「勉強や他のことに割く時間が減ること」です。
当然のことですが、ゲームに費やす時間が増えてしまうと、その分他のことに費やす時間が減ってしまいます。
その結果、宿題をやらない、勉強をしない、習い事に通わない、などの状態に繋がってしまい、学力低下やコミュニケーション障害を招く可能性もあります。
特にオンラインゲームなどは「今このタイミングでやらなければ」という衝動に駆られやすいため、注意しなければなりません。
④ 協調性や社会性に影響する
4つ目は「協調性や社会性に影響すること」です。
ゲームでのコミュニケーションは、オンラインに偏る傾向にあるため、実際の対面でのコミュニケーション能力が低下する危険性があります。
また、表情や声のトーン、身振り手振りといった非言語コミュニケーションの機会が減少し、相手の感情を適切に読み取ったり、自分の感情を適切に表現したりする能力が育ちにくくなることもリスクの1つです。
また、ゲーム内での人間関係は表面的なものになりやすく、深い信頼関係や友情を築く経験が不足しがちです。
⑤ 現実との区別がつかなくなる
5つ目は「現実との区別がつかなくなること」です。
前述したように、ゲームをプレイしすぎてしまうと、現実世界とゲーム内の世界の境界線が曖昧になり、区別がつかなくなってしまいます。
特に暴力的なコンテンツに長時間触れることで、現実での暴力に対する感受性が鈍くなり、問題解決の手段として暴力を選択しやすくなったりする可能性もあります。
これらの感覚は、自分では認識していなくても、自然と考え方や思考が変化する可能性があるため、保護者などからの客観的な視点が非常に重要になります。
子どもの脳の成長や発達に良い影響を与えるもの
本項目では、子どもの脳の成長や発達に良い影響を与えるものについてご紹介します。
本記事でもご紹介した通り、ゲームのやりすぎは、子どもの脳の発達に悪影響を及ぼすだけでなく、日常生活や人との関わり方にも影響します。
とは言え、子どもからゲームを取り上げたからといって、脳の発達が完全に正常化される訳ではありません。
以下は、子どもの脳の発達において特に重要な要素を厳選したものです。
- 十分な睡眠
- バランスの良い食事
- 適度な勉強や新しい知識のインプット
- 様々な価値観に触れる機会
- 他人との会話やコミュニケーション
これらの要素は、いずれも一朝一夕で手に入れることができるものではなく、幼少期〜小学生/中学生頃まで継続的に意識すべきものです。
特に保護者の方は、これらの要素を子どもに与えられるような環境を意識することをオススメします。
ゲーム脳に関する、よくある質問
最後に、ゲーム脳に関するよくある質問について、以下の3つの質問に回答します。
- 子どものゲームの時間はどれくらいが適切ですか?
- 子どものゲームについて親が気を付けるべきポイントは?
- ゲームにはどんな教育的効果がありますか?
① 子どものゲームの時間はどれくらいが適切ですか?
子どものゲームの時間については、各家庭で最適な時間を決める方法が一番です。
学業や他のことに支障が出ていないのであれば、そこまで厳しく制限する必要は無いかもしれませんし、逆に身の回りのことが疎かになってしまっている場合は、ルールなどを設けて時間をしっかりと管理する必要があるかもしれません。
一般的な家庭では、小学生の場合は1日あたり1時間程度、中学生の場合は1日あたり2時間程度まで許容している保護者が多いようです。
② 子どものゲームについて親が気を付けるべきポイントは?
まず、ゲームの内容や対象年齢を確認し、子どもに適したものを選択することが最も重要です。
その上で、ゲームに費やす時間やプレイする時間帯などを決め、子どもを納得させた上で管理することが重要です。
また、ゲームが脳や成長に与える影響などについても子どもにしっかりと伝え、明確な理由のもと制限しているということを正しく伝えることも重要です。
③ ゲームにはどんな教育的効果がありますか?
やりすぎると脳の発達や成長に悪影響を与えるゲームですが、費やす時間や内容によっては頭に適切な刺激を与える場合もあります。
実際に、幼少期の子どもの教育に向けたゲームなども販売されており、ものによっては論理的思考力や問題解決能力を養うことも可能です。
子どもが興味を持つゲームの内容はそれぞれですが、教育や脳への良い影響という観点から、ゲームを選んでみるのも1つの方法です。
ゲーム脳に関するご相談は、子どもブレイン バランスセンターまで
いかがでしたでしょうか。
今回は、子どもとゲーム脳というテーマで、ゲームが子どもの脳の発達に与える影響やゲーム脳になってしまうことによるリスクなどをご紹介しました。
冒頭でもご紹介した通り、子どものゲーム脳は世の中で問題視されていることに加え、長時間ゲームに時間を費やすことは、日常生活にも悪影響を及ぼすことがわかっています。
とは言え、ゲームは子どもにとって大きな楽しみであることも事実であるため、各家庭でしっかりとコミュニケーションをとり、適切なルール作りや対応を意識することが重要です。
また、子どもブレイン バランスセンターでは、ゲーム脳やそれに伴う脳の発達の偏りに関する相談をいつでも受け付けています。
日常生活において子どもの言動や脳の働きについて少しでも不安な気持ちがあるという保護者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。