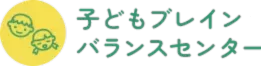【スマホ脳とは?】依存してしまう恐ろしいリスクや解消法について徹底解説!
「スマホ脳ってよく聞くけど、具体的にはどんな状態のことを指すの?」
「子どものスマホ脳やスマホ依存症について理解したい」
私たちが普段日常的に触れているスマホや携帯は、今や生活において欠かせないものとなっています。
しかし、そんな中で近年話題となっているのが「スマホ脳」。
今回は、そんなスマホ脳というテーマに沿って、スマホ脳による症状や影響、スマホ脳を改善するための対処法などについてご紹介します。
また、子どもブレイン バランスセンターでは、スマホ脳や依存症による子どもの脳の発達に関するご相談をいつでも受け付けています。
本記事の内容を読み、子どものスマホ脳に関して不安を感じた方は、ぜひお気軽にご相談ください。
スマホ脳とは
まずはじめに、スマホ脳についてご紹介します。
スマホ脳とは、スマートフォンや携帯の過度な使用によって引き起こされる、脳や身体機能への悪影響を指す言葉です。
スマートフォンや携帯の過度な使用による個人への影響は様々ですが、デジタル機器への依存により、脳の前頭前野の機能が低下することで、判断力や集中力、記憶力などに支障をきたす状態などが代表的な状態として挙げられます。
また、常に新しい情報を求めてスマートフォンを頻繁に確認する習慣により、ドーパミンの分泌が過剰になり、その結果 現実世界での満足感が得られにくくなることも特徴です。
スマホ脳と似た症状に、ゲーム脳が挙げられますが、そちらについては「ゲームは子どもの脳の発達に悪いの?良いの?どうしたら良いの?」にて解説しているので、気になる方はぜひこちらもご覧ください!
【関連記事】
・【境界知能のチェック】具体的な確認手順や診断方法、サポート内容をプロが解説!
・【境界知能でも勉強はできる?】効果的な取り組み方やサポート方法をプロが解説!
スマホによる子どもの脳への影響
次に、スマホによる子どもの脳への影響について簡潔にご紹介します。
スマホを長時間触ることによる脳や日常生活への影響は様々ですが、そんな中でも特に注目されているのが「子どもの脳の発達への悪影響」です。
子どもの脳は、幼少期の頃から触れる様々な物事について考えることで発達していきます。
五感やコミュニケーション、日々の経験など、身の回りからの様々な要素によって脳が刺激され、前頭前野(考える力を司っている部分)が発達します。
しかし、幼少期からスマホに触れる時間が多くなってしまうと、親や友達とのコミュニケーションの機会が十分に得られない、外で遊んで様々なものに触れる機会が減ってしまうなどの影響によって、前頭前野の発達が遅れてしまうのです。
外出する機会があったとしても、スマホを触ってしまうことで運動する機会が減り、結果として体を動かすことによる脳への刺激も減ってしまいます。
また、普段からスマホで調べ物をする習慣は、一見 素晴らしい習慣と思われがちですが、脳を働かせて物事の答えを探す機会が減ることで、考える力が失われてしまうのです。
実際に、スマホを長時間触る子どもの知能や学力が低い傾向にあるという研究結果も発表されています。
近年では、外出先で子どもが駄々をこねたりした際にすぐにスマホを手渡す瞬間を多く目にしますが、そのような習慣は、長期的に見て子どもの考える力の低下に繋がってしまうのです。
【関連記事】
・「【ゲーム脳とは?】子どもの脳の状態や成長に与える影響などについてプロが徹底解説!」
・「【ゲーム依存症が子どもの脳に与える影響は?】リスクや予防法をプロが解説!」
スマホ脳による症状や影響
本項目では、スマホ脳による症状や影響について、以下の4つをご紹介します。
- 目の疲れやドライアイ
- 首や肩のコリ
- 集中力や記憶力の低下
- 不安感情やイライラの増幅
また、普段の生活の中でこれらの症状を感じる方は、スマホ脳に陥っている可能性があるため、ぜひ一度 自分自身の生活や症状を見直してみることをオススメします。
① 目の疲れやドライアイ
スマホ脳による症状や影響の1つ目は「目の疲れやドライアイ」です。
パソコンやiPadなどでも同様のことが起きますが、スマホを長時間見続けていると、画面からのブルーライトによって目が疲れてしまいます。
また、スマホなどの画面を見ている時は自然と瞬きの回数が減ってしまい、その結果ドライアイとなってしまうこともあります。
② 首や肩のコリ
3つ目は「首や肩のコリ」です。
長い間スマートフォンや携帯を触っている姿勢が悪いと、首や肩に過度な負荷がかかってしまい、首や肩のコリを感じてしまうようになります。
また、体全体の姿勢が悪い場合には、背骨や腰の骨にも良くなく、長期的に見て体のバランスが歪んでしまうことがあります。
③ 集中力や記憶力の低下
3つ目は「集中力や記憶力の低下」です。
ニュースやSNS上の写真、友達との会話など、様々な情報のやり取りができるスマートフォンは、勉強や仕事の集中の妨げとなる場合があります。
普段何か他のことをしている最中に、無意識のうちにスマホを触ってしまったり、スマホを触らなければ落ち着かなくなってしまうといった状態を感じる方は、注意が必要です。
また、欲しい情報がすぐに手に入るというスマホの仕組みは、脳内の考える力を低下させ、結果として記憶力の低下を引き起こすリスクがあります。
④ 不安感情やイライラ感の増幅
4つ目は「不安感情やイライラ感の増幅」です。
SNS上での他者との比較や、常に最新情報をチェックしなければならないという思考は、不安感やストレスを増幅させる要因となります。
また、通知音に反応して頻繁にスマートフォンを確認してしまう習慣は、ドーパミン依存的な行動パターンを形成し、結果として落ち着きのなさやイライラ感が増幅される原因となってしまいます。
スマホ脳によるリスク
本項目では、スマホ脳によるリスクについて、以下の4つをご紹介します。
- 脳が疲労してしまう
- 物忘れが多くなる
- 睡眠の質が悪化する
- コミュニケーション能力の低下
これらのリスクは、スマホ脳による症状が悪化することで長期的に体に現れる症状であるため、既にスマホ脳の症状を感じている人は特に注意が必要です。
① 脳が疲労してしまう
スマホ脳によるリスクの1つ目は「脳が疲労してしまうこと」です。
SNSやニュースなど、常に更新され続ける情報を見続けることは、脳の処理能力を疲弊させ、結果として他の作業や仕事の質が低下することに繋がってしまいます。
普段から何気なく見ているスマホの画面でも、そこに映し出される情報によって自然と脳が働き、それが故に意思決定能力や決断力が低下してしまうのです。
② 物忘れが多くなる
2つ目は「物忘れが多くなること」です。
前述した、記憶力が低下してしまう症状とも関連しますが、スマホによってすぐに欲しい情報に辿り着けるという仕組みは、脳内の考える力自体を弱体化させてしまいます。
脳が情報を自発的に記憶し保持しようとする機能が低下してしまうのです。
その結果、普段の日常生活における物忘れが目立ってしまい、「あれ、何をしようとしていたんだっけ?」といった具合に、自分自身の行動すら分からなくなってしまうことがあります。
③ 睡眠の質が悪化する
3つ目は「睡眠の質が悪化すること」です。
特に夜間、就寝前にスマートフォンを使用してしまうと、画面から発せられるブルーライトによってメラトニンの分泌が抑制され、体内時計を狂わせてしまいます。
また、SNSやニュースをチェックする習慣は、脳の興奮状態を助長させ、睡眠自体の質を低下させてしまいます。
④ コミュニケーション能力の低下
4つ目は「コミュニケーション能力の低下」です。
スマートフォンなどによるオンラインでの交流ばかりに慣れてしまうと、対面での人との関わりやコミュニケーションなどにおける能力が低下してしまいます。
文字ばかりのコミュニケーションに慣れてしまうことで、相手の表情や声のトーン、ジェスチャーなどを読み取る能力が欠けてしまうのです。
子どもにスマホを与えるのはよくない?
では、そんなスマートフォンや携帯を子どもに与えるのは良くないのでしょうか。
結論から述べると、スマートフォンの過度な使用は、本記事でもご紹介した通り、脳の発達においても日常生活における影響の面からもあまり良くありません。
とは言え、現代においてスマートフォンなどの電子機器の使用はやむを得ない場面も多々あり、極端に使用を制限してしまうと家族間の関係や、子どもの友人関係にも影響が及んでしまうことがあります。
そのため、保護者や子どもはスマートフォンの過度な使用によるリスクをしっかりと理解した上で、適切なルールに沿ってスマートフォンを使用することをオススメします。
スマホ脳を改善するための対処法
最後に、スマホ脳を改善するための対処法について、以下の4つをご紹介します。
- 使用時間のルールを決める
- 就寝前にスマホに触らない
- スマホやアプリの設定を活用する
- オフラインでの人との交流の機会を増やす
スマホ脳やスマホに依存した状態は、一朝一夕で改善できるものではありませんが、ぜひこれらの対処法を実践してみてください。
① 使用時間のルールを決める
スマホ脳を改善するための対処法の1つ目は「使用時間のルールを決めること」です。
多くの人が肌身離さず持っているスマートフォンは、気付かぬうちに数十分、時には数時間触ってしまうことも多いでしょう。
そのような場合は、スマホに触る時間をルールとして正確に設定することで、スマホに触れる時間を減らすことができます。
また、1日の間で数時間しかスマホを触ることができないというルールを設けることで、無意識のうちになんとなくSNSを眺めてしまうなどの状態を避けることができるでしょう。
② 就寝前にスマホに触らない
2つ目は「就寝前にスマホに触らないこと」です。
特に就寝前の時間帯は、無意識のうちに長時間スマートフォンを触ってしまいがちです。
翌朝早く起きなければならないのに、気づいたら30分、1時間と時間が経ってしまった経験をした人も少なくないでしょう。
体内時計が狂うことや脳の覚醒状態を極力抑えるためにも、就寝前にスマートフォンに触れることは避けることをオススメします。
③ スマホやアプリの設定を活用する
3つ目は「スマホやアプリの設定を活用すること」です。
現代のスマートフォンやアプリには、スマホの使用時間や適切な利用をサポートする機能が多く用意されています。
例えば、画面の色調を調整するブルーライトカット機能やアプリごとの使用時間制限設定ができるもの、通知の一括管理機能などが挙げられます。
また、通知が気になってスマートフォンをすぐに触ってしまうという状態を避けるためにも、作業や仕事に集中している時は通知を切っておくなどの対策が重要です。
④ オフラインでの人との交流の機会を増やす
4つ目は「オフラインでの人との交流の機会を増やすこと」です。
オンライン上での交流に偏りがちな方々にとって、現実世界で対面で人と接する機会はスマホ脳を改善するための良い方法です。
友人や家族との食事、スポーツ、趣味、サークルに参加するなど、コミュニケーションの機会を積極的に作るチャンスは数多くあります。
対面でのコミュニケーションは、人の表情や声のトーン、身振り手振りなどの非言語コミュニケーションを通じて、より豊かな人間関係を築くことができるため、脳にとっても様々な刺激があるでしょう。
子どものスマホ脳に関するご相談は、子どもブレイン バランスセンターへ
いかがでしたでしょうか。
今回は、スマホ脳について、スマホ脳による症状や影響、スマホ脳を改善するための対処法などについてご紹介しました。
スマホ脳は、子どもや大人に関わらず、多くの現代人が抱えている問題です。
中でも子どもの場合は、脳の発達における重要な時期であるため、スマホを触りすぎてしまうことによる悪影響については、保護者が正しく理解しておく必要があります。
とは言え、スマホが生活の一部になっている現代において、常にスマホから離れて生活することは難しいのも事実です。
そのため、スマホや携帯、電子機器などに触れる時間は最小限にとどめ、可能な限り人との対話やその他頭を使うような物事に時間を費やすことをオススメします。
また、子どもブレイン バランスセンターでは、子どものスマホ脳やゲーム脳に関するご相談をいつでも受け付けています。
子どものスマホ脳やゲーム脳でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください!