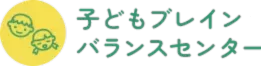【スマホ脳とは?】スマホが脳や前頭葉に与える影響や負担について徹底解説!
「スマホ脳って何?」
「スマホが脳や前頭葉に与える影響について知りたい」
スマホを多く使う方の中には、スマホが脳に与える影響やその対策について気になっている方も多いのではないでしょうか。
近年では、複数の医師や研究者が、スマホを長時間使うことで仕事への意欲や集中力が低下するなどの弊害が生じると指摘しています。
本記事では、スマホ脳と前頭葉について以下の点を中心に詳しく解説します。
- スマホ脳の概要
- スマホを使うことで前頭葉が疲れる理由
- 前頭葉が疲れることで起こる症状
- スマホ脳から脱却するための方法
スマホが脳や前頭葉に与える影響について興味のある方は、参考にしていただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
スマホ脳とは?
はじめに、スマホ脳の概要をご説明します。
スマホ脳とは、スマホの使い過ぎで脳に疲労が溜まり、集中力や記憶力、仕事への意欲などが低下している状態です。
スマホでのウェブ検索やSNSの閲覧が習慣化すると、数多くの情報に触れることになります。
次から次へと情報が流れ込んでくるため、脳は短時間で多くの情報を処理しなければなりません。
このように、多くの情報に触れ、高速でインプットする中で次第に脳が疲弊し、情報処理機能が低下します。
それにより、集中力や記憶力、意欲やコミュニケーション能力といった機能の働きが悪くなってしまうのです。
【関連記事】
・【スマホ脳とは?】依存してしまう恐ろしいリスクや解消法について徹底解説!
・【ゲーム脳とは?】子どもの脳の状態や成長に与える影響などについてプロが徹底解説!
前頭葉の役割と重要性
次に、前頭葉の役割と重要性について解説します。
前頭葉とは、大脳の一番手前に位置する部分です。
思考や言語、感情や理性などをつかさどる、人間として生きるのに最も重要な器官だといっても過言ではありません。
前頭葉の働きにより、自分の考えを言語化して相手に伝えたり、衝動を抑えて協調性を示したりといった行動が可能になります。
前頭葉の機能が低下すると、意欲が低下したり、記憶力が低下したり、感情的になったりといった症状が現れます。
これらの症状が現れると、他者への気遣いなどができず、人として社会的な生活を送るのが困難になるでしょう。
前頭葉が正常に機能しているおかげで、私たちは安定した社会生活を送れているともいえます。
【関連記事】
・【ゲームは脳トレになる?】ゲームが脳に与える影響や子どもの成長について徹底解説!
・ゲームは子どもの脳の発達に悪いの?良いの?どうしたら良いの?
スマホを使うことで前頭葉が疲れる理由
次に、スマホを使うことで前頭葉が疲れる理由について解説します。
前述した通り、スマホでウェブ検索やSNSを利用していると数多くの情報に触れるため、その分脳は多くの情報を処理しなければなりません。
そのため、朝から晩まで頻繁にスマホに触れていると、脳が十分な休息を取れず、次第に疲弊していきます。
疲労によって脳の司令塔とも呼ばれる前頭葉への血流が減り、うっかりミスが多くなったり、感情のコントロールができなくなるのです。
【関連記事】
・【何ができない?】境界知能を持つ子どもの苦手分野や向き合い方をプロが解説!
前頭葉が疲れることで起こる症状
ここでは、前頭葉が疲れることで起こる症状について、以下の4つをご紹介します。
- 注意力や集中力の低下
- 感情のコントロール力の低下
- 記憶力の低下
- 精神的なストレスの増加
① 注意力や集中力の低下
前頭葉が疲れることで起こる症状の1つ目は「注意力や集中力の低下」です。
前述したとおり、スマホから絶え間なく通知や情報が流れ込んでくると、それらを処理するために前頭葉が過剰に働くことになります。
結果として前頭葉が疲弊し、注意を持続させる力やひとつのことに集中する力が低下するのです。
注意力や集中力が低下すると、簡単なタスクにもかかわらずミスが増えたり、相手と会話している時に別のことを考えて思考がまとまらなくなったりするようになります。
②感情のコントロール力の低下
2つ目は「感情のコントロール力の低下」です。
前頭葉は、理性的な判断をしたり感情を抑制したりといった、人が生活を送る上で欠かせない役割を果たしています。
しかし、スマホの頻繁な使用により前頭葉が疲れると、感情をコントロールする機能が低下します。
瞬間的な快感を最優先で追い求め、先々の目標に向けてコツコツ努力するというような自制心が働きにくくなるのです。
その結果、スマホ使用に対する欲求を抑えられなくなったり、感情のコントロール力が低下することで怒りっぽくなったりすることに繋がります。
③記憶力の低下
3つ目は「記憶力の低下」です。
前頭葉は外から入って来る情報を処理し、記憶として保管する機能を持っています。
さらに、保管した記憶を呼び起こし、行動に反映させるといった重要な役割も果たします。
スマホにより前頭葉が疲弊して記憶力が低下すると、情報処理のために一時的に記憶することや、適切な単語が思いつかず流ちょうに話すことが難しくなるのです。
④精神的なストレスの増加
4つ目は「精神的なストレスの増加」です。
スマホを通じて多くの情報を受け取ることで、前頭葉に過剰な負担がかかります。
次第に脳が情報を処理しきれなくなり、前頭葉が疲弊すると、イライラしやすくなったり、他人に対して攻撃的になったりするのです。
その結果、精神的なストレスが増え、日常生活が送りにくくなることに繋がります。
また、夜遅くまでスマホを触っていると、脳が十分な休息を取れません。
睡眠の質や量が不足し、結果として心身の不調にも繋がるのです。
スマホ脳から脱却するための方法
最後に、スマホ脳から脱却するための方法について、以下の5つをご紹介します。
- 時間制限を設ける
- 目的をもって利用する
- ボーッとする時間を作る
- 代替行動を見つける
- 睡眠の確保を最優先する
①時間制限を設ける
スマホ脳から脱却するための方法の1つ目は「時間制限を設けること」です。
まずは自分が1日にどの程度スマホを利用しているのかを振り返ってみましょう。
iPhoneならスクリーンタイムといった機能があり、アプリごとの使用時間を確認できます。
自分の利用状況が把握出来たら、頻繫に利用するアプリの使用に時間制限を設けます。
SNSは1日30分、ゲームは1日1時間以内などと設定し、それを守る努力をしてみましょう。
もし自分だけで制限するのが難しい場合は、各アプリに搭載されている使用時間を制限する機能を使うのもおすすめです。
②目的をもって利用する
2つ目は「目的をもって利用すること」です。
目的もないのに、何となくスマホを触ってしまう方も多いのではないでしょうか。
よくあるのが、SNSアプリを閲覧して終了した直後に、再度SNSアプリを開いてしまっているという行動です。
例えば、何か調べものが必要だとか、誰かに連絡する必要があるなどの目的をもって利用するのがベストです。
目的がある時だけの使用に留めておけば、過剰にスマホを触ることもなくなります。
③ボーッとする時間を作る
3つ目は「ボーッとする時間を作ること」です。
1日5分でもよいので、何もせずボーッと過ごす時間を作るだけでもスマホ脳から脱却できます。
ボーッとしている間に脳がしっかりと休まり、疲労が回復するのです。
また、より効果的な方法を探している方は、ボーッとするだけではなく、瞑想やマインドフルネスを取り入れるのもおすすめです。
瞑想やマインドフルネスを活用することで、集中力や注意力を回復できる上、スマホから注意を引き離すトレーニングにもなります。
④代替行動を見つける
4つ目は「代替行動を見つけること」です。
つまり、スマホに頼らず、別の楽しみを見つけるということです。
例えば、読書や料理、スポーツ、楽器の練習などが挙げられます。
中でもアウトドア活動や体を動かす趣味は、スマホと距離がおける上、リフレッシュ効果もあり一石二鳥です。
また、家族や友人との交流を増やすのもおすすめの方法です。
スマホを通じてではなく、リアルなコミュニケーションを図ることでより深い満足感が得られるでしょう。
⑤睡眠の確保を最優先する
5つ目は「睡眠の確保を最優先すること」です。
スマホ脳から脱却するためには、質と量、両方を意識した睡眠の確保が大切です。
睡眠をとることで、疲労を回復したり、脳細胞が修復されたりといったポジティブな効果が得られます。
夜遅くまでスマホを触っていると、睡眠時間が少なくなり、脳が回復するのに十分な睡眠時間が確保できなくなります。
そのため、寝る2時間前からスマホは触らない、といったルールを決めるのも有効です。
スマホ脳 前頭葉まとめ
ここまで、スマホ脳についてご紹介しました。
要点を以下にまとめます。
- スマホ脳とは、スマホの使い過ぎで脳に疲労が溜まり、集中力や記憶力、意欲などが低下している状態
- スマホの使い過ぎによる疲労で前頭葉への血流が減り、働きが鈍くなる
- 前頭葉が疲れると、注意力や集中力が低下したり、感情のコントロール力が低下したりするなどの症状が現れる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。